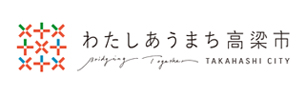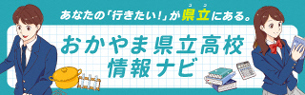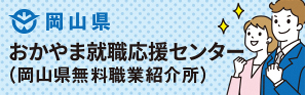Blog たか高Diary
たか高の今を伝えます
家政科1年次「保育基礎」_やさしさをページに込めて、高校生の手作り絵本展@高梁高校図書館
私たち1年次生は、「保育基礎」の授業で手作り絵本を制作しました。
この授業では、子どもの発達や興味に合わせた内容を自分たちで考え、それぞれテーマを決めて絵本を作りました。
完成した作品は、現在本校図書館で展示しています!

✏️制作の工夫
制作のときに特に工夫したのは、三歳児が楽しみながら見られるように、問いかけの言葉「どれがすき?」を入れたことです。
この言葉を入れることで、子どもが自分の考えを言葉で表したり、読む人とのやりとりを楽しんだりできるようにしました。
また、問いかけがあることで、最後まで興味をもって読んでもらえるようにしました。
子どもが「楽しい!」と思える絵本にするのは大変でしたが、完成したときは思っていたよりかわいく仕上がり、とてもうれしかったです。
制作の途中では、「どんな言葉なら子どもが笑顔になるかな」と悩むこともありましたが、ページをめくるたびにワクワクできるように意識して作ったので、「これならきっと楽しんでもらえるかも」と思えて、がんばってよかったなと感じました。
展示を見てくれた人の感想
展示を見てくれた人からは、
「ページの構成がわかりやすく、『どれがすき?』という繰り返しがあることで読み進めるのが楽しい」
「全体の色使いがやさしく、三歳くらいの子どもが落ち着いて見られる雰囲気になっていてよかった」
といった感想をいただきました。
自分の工夫が伝わってうれしかったです!
友達の作品から学んだこと
友達の作品を見て、磁石を使ったしかけ絵本や、物語絵本などがあり、とてもおもしろいと思いました。
磁石を使うことで「くっついた!」「はなれた!」という動きが生まれ、子どもが夢中になれそうだと感じました。
また、物語絵本では登場人物の気持ちやストーリーの流れを感じながら読むことで、子どもの想像力が育つと思いました。
活動を通して学んだこと
この活動を通して学んだのは、「子どもの目線で考えることの大切さ」です。
大人がいいと思うものと、子どもがいいと思うものはちがうことがあります。
でも、子どもの気持ちになって考えると、「どんな色が目をひくかな」「どんな言葉ならわかりやすいかな」といった工夫ができるようになります。
また、「おもしろい!」「やってみたい!」と感じるしかけや問いかけを入れることで、子どもが夢中になって最後まで楽しめる絵本になると感じました。
✨これからに向けて
今回の経験を通して学んだ「子どもの立場で考える力」を、これからの保育の授業や実習でも生かしていきたいです。
子どもが「これ楽しい!」「もっと見たい!」と思えるような関わりを意識しながら、一人ひとりの気持ちに寄りそえるようになりたいです。
そして、仲間と協力しながら、子どもの笑顔があふれるような活動を考えていきたいと思います。
Grow with Grit!(やり抜く力)= Perseverance(忍耐力)× Passion(情熱)
#高梁高校 #たかこう #保育基礎 #手作り絵本 #ものづくりの楽しさ